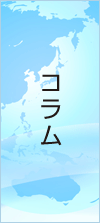コラム
伝わるためには?
言葉は難しいですね。同じことを言っていても、伝わったり、伝わらなかったり。
私の話をしましょう。
以前、働いていた国連の研修所では研修員が多国籍のため、基本的に講義は英語でおこなわれます。ある日、英語が流暢なAさん(英検1級)が講義をしました.専門用語を駆使し、綺麗な発音で流暢に講義をしていたのですが、どうも研修員が集中しておらず、あまり伝わった感じがしません。Aさんは自分の発音が悪いのか文法に間違いがあるのか色々気にしていました。すると、横で見ていたBさんが説明を付け加えはじめました.Bさんは英語は不得手だと言っており、語彙も文法もあまり洗練されてはいません。しかし、研修員たちはしっかりと聞き取り、内容が伝わったようでした。
何が違ったのでしょう?
Bさんの話し方を見ると、研修員の目を見て、身振り手振りで一生懸命に伝えています。また、使う言葉は平易なのですが、具体的な例を挙げています。英語が母国語ではない多国籍の研修員にはかえって理解しやすいようでした。結局は流暢な言葉よりも、伝えたいと思う気持ち、伝えようと努力すること、研修員の立場に立った言葉の選択が重要だったのです。
私のささやかな経験は犯罪心理学とどのような関係があるのでしょう?
いま、犯罪者処遇に効果的なプログラムの条件として、犯罪心理学者であるAndrewsらが提唱したRNR原則(Risk, Needs and Responsivity Principle)に則っていることが必要と言われています。これは、介入の対象としてRiskの高い者が選ばれるべきであり、Needはたとえば、薬物使用や態度など犯罪に関係するNeed領域に介入すべきであるとしています。しかし、対象者が受け止めやすい方法で介入を実施するというResponsivity(反応性)というのは腑に落ちないものを感じていました。
ここで冒頭の話が思い浮かんだのです。
実施される介入がエビデンスに基づく内容であり、その実施方法がマニュアルから外れないということ、つまりは正当なものである必要があることはもちろんなのですが、その実施にあたっては難しい言葉を駆使したり一見洗練されたやり方で行うことよりも、その内容が対象者に伝わるように、真摯に、そして対象者が受け止めやすいやりかたで行う必要があるということなのではないかと思うのです。
とはいえ、言うは易く、行うは難し、です。結局は精進しかないのだなあ、と思うところです。(新海浩之)